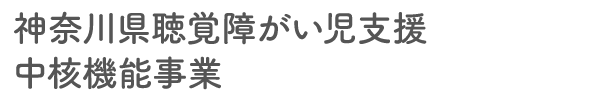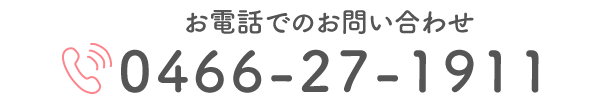きこえにくいお子さまのために
新生児スクリーニングでリファー(要再検査)になった赤ちゃんのご家族へ

新生児スクリーニングは、外見ではわかりにくい耳の聞こえにくさを早期に発見し、適切な専門機関や医療機関につなげる目的で行われます。
この検査でリファーであっても、すぐにお耳に異常があるとは判断できません。必ず精密検査が受けられる医療機関を受診しましょう。
お子さんの聞こえが気になったら

新生児スクリーニングがパスであっても、感染症やそのほかの病気などで後から耳の聞こえが悪くなることがあります。
突然の大きな音に反応しないなどお子さんのきこえで気になることがありましたら、こちらからお問い合わせください。
精密検査について
新生児聴覚スクリーニングでリファー(要再検査)となった場合、聞こえの状態を詳しく知るために精密検査を受ける必要があります。
精密検査実施医療機関で耳鼻咽喉科医の診察(耳の中など)を受け、検査機器を使った聴性脳幹反応(ABR)や聴性定常反応(ASSR)を行います。検査はお子さんが眠った状態で行います。音を出すヘッドホンや脳波を見るための端子を皮膚に取り付けますが痛みは伴いません。また、楽器音や検査音を使ってお子さんの反応を見る検査(BOAやCOR)やご家族からの問診をもとに慎重に診断されます。
精密検査までにご心配事などありましたら、こちらからお問い合わせください
補聴について

きこえを補う方法としては、主に2つあります。
・補聴器
補聴器に内蔵されたマイクでひろった音を増幅して耳に伝えます。
お子さんが耳にかけて使うものなどで、手術は必要ありません。
・人工内耳
音をひろう体外装置と手術で埋め込む体内装置をつなげて使います。
耳の奥の蝸牛に埋め込んだ電極を通じて電気信号化した音を脳に伝えます。
体内装置(インプラント)を埋め込む手術が必要です。
教育や療育について

お子さんの成長にとって大切なことは、ご家族のもとで安心と安全と愛情をたくさん感じることです。お互いに「通じた」「楽しい」と思える経験の積み重ねがお子さんの心とことばを育んでいきます。
しかし、お子さんにきこえにくさがあることでお子さんの感じ取り方が違うなど、お子さんへの伝え方に悩んだり不安に感じることもあるかもしれません。
お子さんの健やかな成長のための様々なサポートが受けられる施設があります。お子さんの様子に合わせたコミュニケーション手段や進路などを一緒に考えていきましょう。
コミュニケーションについて

きこえにくいお子さんとのコミュニケーション方法はいろいろあります。
声で話しかける以外にも表情、身振り、手話、筆談などがあります。
どれか一つを選ばなければならないということはなく、楽しくやりとりできる方法を考えていきましょう。
聴力検査について

センターではお子さんの状態に応じた聴力検査を行っています。
・BOA
楽器などを使って音に対する反射や行動を観察します。首の座っていないお子さんにも実施することができます。
・COR
検査音と視覚的な刺激(おもちゃなど)も使って、お子さんの音への反応を測定します。首の座った頃から実施できます。
・ピープショウテスト、遊戯聴力検査
検査音に対してお子さん自身がボタンを押したり、玉を移動させたりすることで聴力を測定します。